# Web3プロジェクトにおける一般的な高リスク運営モデルの分析Web3の分野では、一部のプロジェクトが規制責任を回避するために、一見巧妙で実際には危険な運営戦略を採用しています。本稿では、一般的な高リスク運営モデル3つを分析し、実例を交えてその潜在的なリスクについて説明します。## "アウトソーシング"モデルの危険性多くのWeb3プロジェクトは、コアビジネスをアウトソーシングする傾向があり、責任の境界を曖昧にしようとしています。しかし、規制当局が注目しているのは、表面的な契約ではなく、実際の意思決定者と受益者です。いわゆる第三者サービスプロバイダーとプロジェクトチームの間に利害関係や支配関係が見つかった場合、このアウトソーシング戦略は逆効果になる可能性があります。例えば、あるケースでは、プロジェクトチームが複数の法人を設立し、一部の作業を外部に委託していたにもかかわらず、規制当局は調査を通じて、重要な意思決定が依然として親会社によって管理されていることを発見しました。このような「形式的分割」は責任を回避することができず、むしろ意図的に規制を回避しようとする証拠と見なされました。真に効果的なコンプライアンス戦略は、プロジェクトの初期段階でどの機能をアウトソースできるか、どの機能が内部で担う必要があり、責任主体を公開するかを明確に区分すべきです。## "多地登録+分散ノード"のリスクいくつかのプロジェクトは、規制の緩い国に登録し、グローバルにノードを展開していると主張して、分散型のイメージを作り上げています。しかし実際には、そのような構造のほとんどは依然として高度に集中管理されており、規制の詳細な調査に耐えることが難しいです。規制当局は、国境を越えた調査を行う際に、実質的な支配者の所在地や重要な行動が行われた場所を優先的に追跡します。分散型ノードの技術的な展開は、運営の実質を隠すことはできません。最近のいくつかの法的事例は、ユーザーの相互作用やインフラの展開が存在する限り、規制が介入する可能性があることを示しています。一部の地域の規制当局は、"実際の管理場所"と"主要管理者の実際の居住地"の開示を要求し始めており、"無国籍"の主張が成立しにくいことを示しています。複雑なシェル構造を構築するよりも、プロジェクトの実質的な責任者の責任と規制義務の分配を明確にすることの方が法的リスクを低減するのに役立ちます。## "オンチェーン公開≠無人運営"の誤解一部の技術チームは、スマートコントラクトがデプロイされた後、プロジェクトから"切り離される"と考え、技術によって法的責任の分離を試みています。しかし、規制当局はこの"技術は免責"という見解には同意しません。実際には、オフチェーンの行動が規制当局の判断の責任の所在の核心です。誰がマーケティングを開始し、広告を組織し、流通経路を制御するかが重要な要素です。コードに管理者がいなくても、契約が自由に呼び出される場合でも、プロジェクト側がトークンを推進し、インセンティブを設定し、コミュニティを維持し、資金を受け入れている限り、その運営のアイデンティティは消すことができません。最近のいくつかの法律事例や規制声明は、「行動指向」の判断論理を強調し、オフチェーンのプロモーションや配布経路を重点的な審査項目として挙げています。特に、KOL、エアドロップ、取引所上場などの方法で行われる「促進的発行」のモデルは、ほぼ典型的な運営行為と見なされています。## まとめ規制の焦点は、表面的な構造から実際のコントロール関係に移っています。Web3プロジェクトが本当に必要としているのは、複雑な構造設計ではなく、責任とコントロールの境界を明確に定義することです。リスクを隠すために「構造ゲーム」を試みるよりも、最初からレジリエンスと説明可能性を持つコンプライアンスアーキテクチャを構築する方が良いでしょう。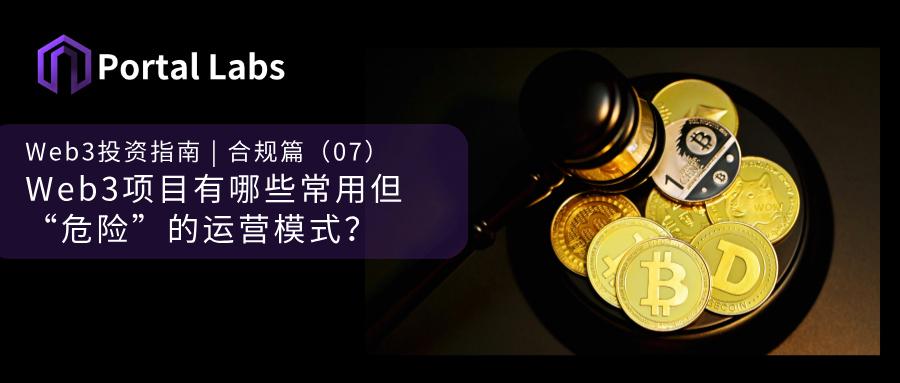
Web3プロジェクトの3つの高リスク運営モデルの分析と事例警告
Web3プロジェクトにおける一般的な高リスク運営モデルの分析
Web3の分野では、一部のプロジェクトが規制責任を回避するために、一見巧妙で実際には危険な運営戦略を採用しています。本稿では、一般的な高リスク運営モデル3つを分析し、実例を交えてその潜在的なリスクについて説明します。
"アウトソーシング"モデルの危険性
多くのWeb3プロジェクトは、コアビジネスをアウトソーシングする傾向があり、責任の境界を曖昧にしようとしています。しかし、規制当局が注目しているのは、表面的な契約ではなく、実際の意思決定者と受益者です。いわゆる第三者サービスプロバイダーとプロジェクトチームの間に利害関係や支配関係が見つかった場合、このアウトソーシング戦略は逆効果になる可能性があります。
例えば、あるケースでは、プロジェクトチームが複数の法人を設立し、一部の作業を外部に委託していたにもかかわらず、規制当局は調査を通じて、重要な意思決定が依然として親会社によって管理されていることを発見しました。このような「形式的分割」は責任を回避することができず、むしろ意図的に規制を回避しようとする証拠と見なされました。
真に効果的なコンプライアンス戦略は、プロジェクトの初期段階でどの機能をアウトソースできるか、どの機能が内部で担う必要があり、責任主体を公開するかを明確に区分すべきです。
"多地登録+分散ノード"のリスク
いくつかのプロジェクトは、規制の緩い国に登録し、グローバルにノードを展開していると主張して、分散型のイメージを作り上げています。しかし実際には、そのような構造のほとんどは依然として高度に集中管理されており、規制の詳細な調査に耐えることが難しいです。
規制当局は、国境を越えた調査を行う際に、実質的な支配者の所在地や重要な行動が行われた場所を優先的に追跡します。分散型ノードの技術的な展開は、運営の実質を隠すことはできません。最近のいくつかの法的事例は、ユーザーの相互作用やインフラの展開が存在する限り、規制が介入する可能性があることを示しています。
一部の地域の規制当局は、"実際の管理場所"と"主要管理者の実際の居住地"の開示を要求し始めており、"無国籍"の主張が成立しにくいことを示しています。複雑なシェル構造を構築するよりも、プロジェクトの実質的な責任者の責任と規制義務の分配を明確にすることの方が法的リスクを低減するのに役立ちます。
"オンチェーン公開≠無人運営"の誤解
一部の技術チームは、スマートコントラクトがデプロイされた後、プロジェクトから"切り離される"と考え、技術によって法的責任の分離を試みています。しかし、規制当局はこの"技術は免責"という見解には同意しません。
実際には、オフチェーンの行動が規制当局の判断の責任の所在の核心です。誰がマーケティングを開始し、広告を組織し、流通経路を制御するかが重要な要素です。コードに管理者がいなくても、契約が自由に呼び出される場合でも、プロジェクト側がトークンを推進し、インセンティブを設定し、コミュニティを維持し、資金を受け入れている限り、その運営のアイデンティティは消すことができません。
最近のいくつかの法律事例や規制声明は、「行動指向」の判断論理を強調し、オフチェーンのプロモーションや配布経路を重点的な審査項目として挙げています。特に、KOL、エアドロップ、取引所上場などの方法で行われる「促進的発行」のモデルは、ほぼ典型的な運営行為と見なされています。
まとめ
規制の焦点は、表面的な構造から実際のコントロール関係に移っています。Web3プロジェクトが本当に必要としているのは、複雑な構造設計ではなく、責任とコントロールの境界を明確に定義することです。リスクを隠すために「構造ゲーム」を試みるよりも、最初からレジリエンスと説明可能性を持つコンプライアンスアーキテクチャを構築する方が良いでしょう。